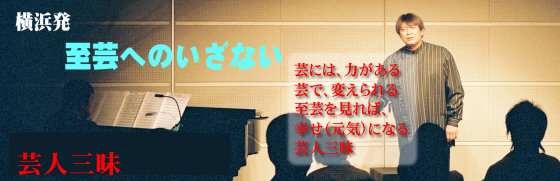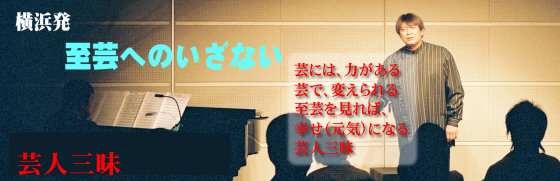この芸人を見ないうちは死ねない
芸人三昧(旧:趙博を応援する会)は、趙博さんをはじめとして、
今見ておかないと後悔すること必至の芸人を紹介しています。
ぜひ生の舞台でご覧になることをお勧めします。芸は映像や写真で味わうことはできません。芸人が発する気が芸の本質だからです。芸は見るものではありません。感じるものです。
●浪曲師 国本武春(くにもと・たけはる)
客のツカミはこうやってやるのだという技(わざ)を見せてくれる「浪曲掛声教室」は浪曲を初めて聞くという人もいっぺんにトリコにしてしまう魔法を見るようです。術にかかる心地よさはユリ・ゲラーのハッタリよりもすごい。はっと気がついたら「待ってました」と声を張り上げている自分がいます。それがまた気持ちいいのです。
国本武春は声がいい、せつない、心にしみてくる。
●一人コント 松元ヒロ(まつもと・ひろ)
いま人気急上昇のお笑い芸人。人気という化け物を、いま松元ヒロのライブ会場で実感できます。その勢いは恐ろしいぐらい。
●一人コント オオタスセリ(おおた・すせり)
みかけは恐いが、そのやさしさに気づいたらオオタスセリといる空間がすごく心地よくなります。
「ストーカーと呼ばないで」の純情に気づいたら、もう涙なしではオオタスセリを聞けません。
●落語 立川志の輔(たてかわ・しのすけ)
数百人も入るホールのお客の気持ちをただ一点、その口許に引きつけてしまう志の輔の芸のすごさを堪能できます。
芸を楽しむということは芸人にたぶらかされるということですから、数百人をたぶらかす志の輔の恐さも同時に体験できます。
●一人シェークスピア 楠美津香(くすのき・みつか)
題名だけは聞いたことはあるがほとんどの人が見たことがないというシェークスピアの芝居を、なんと、たった一人と扇子数本を使い分けて演じてしまいます。かずかずの名セリフが登場する場面は納得の連続です。
日本で一番教養度が高い芸です。
●紙切り 林家二楽(はやしや・にらく)
女アナウンサーの外山恵理さんがその紙切りを見て泣いていました。回りをみると感性の豊かなお客さんは男女を問わず涙している光景を見ることができます。これを見て泣けなくなったらもう老境だといっていいでしょう。感性が若いうちなら間違いなく泣けます。
胴元は二楽のメクリを見ただけで涙がにじんでくるといいます。
●なんといっていのか だるま食堂(だるましょくどう)
コント集団でもないし、駄洒落教室でもないし、この3人組の美女集団をなんといったらいいのかわかりませんが、美人を3人まとめて見るだけでも元気になってきます。
●一人コント モロ師岡(もろ・もろおか)
一人でコントをします。笑わせながら、やがてそれが心にジーンとくるのです。それは落語でも同じですが、モロ師岡はその落語さえも背広を着てやるのです。扇子と手拭いの替わりに手帳と万年筆を使ってやります。
●俗曲 柳家紫文(やなぎや・しもん)
粋(いき)と気障(きざ)は紙一重ですが、紙一重で粋をみせてくれるのが紫文です。名セリフというか名フレーズというか「その日、火付け盗賊改め方長谷川平蔵が」と口にするとその先を知っているお客さんがたまらずふきだしてしまうのはパブロフの犬状態になっているからです。
いうならば日本のパブロフ先生です。
多くの芸人は舞台衣装を脱ぐと小汚い感じがするジーンズなんか穿いてたりしますが、着物を着替えた紫文の格好はお洒落です。
●曲独楽 三増紋之助(みます・もんのすけ)
胴元が三増紋之助の弟子の三増れ紋(みます・れもん)と舞台を一緒したことがあります。といっても一番前の席で見ていたら指名されて舞台に上がっただけですが。
紋之助の芸ではとなりのトトロが出てきます。
●奇人 小沢昭一(おざわ・しょういち)
めったにやらないハーモニカですが、それを聞くと若くない人はおしっこの通りがよくなるということで人気があります。すっきりするからです。寄席でやると便所がこむのでやめてくれと席亭からいわれているとかそうでないとか。
●関西落語 桂あやめ(かつら・あやめ)
あやめはおもしろい。寄席に通っている人ならその一言で通じます。みんながそう思う噺家は少ないでしょう。関西の女の噺家です。
こういう人と出会えるから寄席通いがやめられません。
●関西万歳 姉様キングス(あねさまきんぐす)
姉様キングスの一人が実は桂あやめです。これは実際に聞いてみないと、というより見てみないとわからない二人組。その視覚効果のほうがおかしいかもしれません。
●落語 林家彦いち(はやしや・ひこいち)
横浜にぎわい座の地下にある小ホール「のげシャーレ」での独演会を常に満席にしてきた男が9月に席数が多い芸能ホールへ進出。SWAのメンバーで元極真会館の門下生だったこともある猛者で極真魂と落語魂の両者を合わせ持つ男。
「SWA」とは、創作話芸アソシエーションの略。創作落語の素晴らしい世界へ案内してくれます。
●法律漫談 ミスター梅介(みすたーうめすけ)
天皇陛下には苗字がありません。梅介も苗字がありません。ひょっとして高貴な身分の方なのかもしれません。
あるいはミスターが苗字なのか。すると外国人とのハーフなのかもしれません。法律で漫談ができるのは日本では梅介ただ一人です。
インテリと芸人のハーフであることは間違いありません。
●コント集団 ザ・ニュースペーパー(ざ・にゅーすぺーぱー)
寄席の定義は、テレビや新聞といった建前の場では絶対言えない、書けない本音を語る場であるということです。
落語で盲をわざわざ目のご不自由な人とは言い換えません。枕では当世の風潮に合わせて目のご不自由な皆さんをなぞらえて、頭のご不自由な賢明な皆さんとか、お顔のご不自由な美女の皆さんとくすぐることはありますが、羽織を脱いでからは盲といいます。
なぜかというと、目のご不自由な人というと言葉のリズムが乱れるので聞いていて汚いからにほかなりません。耳が汚れるというわけです。
寄席の芸の上手下手はリズムが心地よいか、乱れているかの違いなのです。亡き志ん朝はそのリズムが良かった。
ザ・ニュースペーパーは世相をリズミカルに斬っていきます。
テレビや新聞がわざと伏せている真実にコントで迫ります。建前報道のもどかしさで鬱積したイライラを一気に解消してくれるテンポのいいザ・ニュースペーパーのコントを見ると心がすっきりします。
その快感は病み付きになります。
松崎菊也、すわ親治、松元ヒロといった芸人を輩出している集団ですから、そのインテリ度はかなり高い集団であることがわかると思います。
●講談 神田香織(かんだ・かおり)
庶民の幸せを願い、音響効果と照明を取り入れた「立体講談」に取り組む美人講談師。
演目「チェルノブイリの祈り --未来への物語--」の孤独な人間の声は、異性と一緒に観に行った時のその人の泣き顔を観るのも楽しみの一つ。
誰かの台詞じゃないが、この演目を観て「泣かねぇのは人間じゃねぇ」。
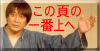
|